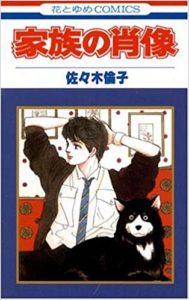正しく恋に落ちないこと――佐々木倫子の「君の名は」 しだゆい
正しく恋に落ちないこと――佐々木倫子の「君の名は」
しだゆい
昨年、新海誠監督の『君の名は。』がおおいに流行した。このタイトルは、周知のとおり敗戦まもない1952年から放送されこちらも当時おおいに流行したというラジオドラマ『君の名は』を下敷きにしている。『君の名は』から『君の名は。』へ――これは京マチ子から今日マチ子へのそれにも匹敵するエポックメイキングな(知名度のうえでの)交代劇であったと思うが、ここではそのいずれとも隔たったところで、流行とは無縁にひっそりと著されたもう一つの「君の名は」を取り上げたい。それは『動物のお医者さん』で知られる漫画家・佐々木倫子の初期連作「忘却」シリーズのなかの一篇である。
佐々木の「忘却」シリーズは、視力も記憶力も特に問題ないにもかかわらずなぜか人の顔を覚えるのが異様に苦手な高校生・黒田勝久を主人公とする各話読み切りのコメディ作品だ。当然ながらどのエピソードも勝久が誰かの顔を覚えられない、あるいは思い出せないことが話を動かすギミックとなっているのだが、ここで論じる「君の名は」は、この基本設定がもっともシンプルかつ効果的に用いられたシリーズきっての佳作であると思う。
家族で山菜取りに来た勝久が愛犬・ルイと木の下で休んでいると、ふいに近くの茂みから物音がして大きなヒグマが現れる(舞台は北海道)。目を逸らすこともできず、今さら死んだふりもできず、かといって逃げれば追われるという膠着状態のさなか、突如カンシャク玉が爆発、砂埃の舞うなか何者かに手を引かれ勝久とルイはヒグマから逃げ出すことに成功する。助けてくれたのは見知らぬショートカットの少女。「もうだいじょうぶだと思うけどこれあげる」と予備のカンシャク玉を手渡し颯爽と去りかけるところを呼び止め、勝久が「君の名は…?」と尋ねると、彼女は少し考えたのち「…じゃあ一か月後にここで会うことにしましょう」と答えるのだった。
この少女は名を浅羽莢子といい、実は勝久と同じ高校に通う同級生、しかもかねてより彼にほのかな恋心を抱いていた――「みんなは黒田くんのことをトンチンカンな人だと言うけれど/私はそれほどとも思わない」。目を閉じ、思わずほころぶ口許をしとやかにノートで隠しながらのモノローグでなければ恋しているとも察しがたい、きわめて絶妙な表現だ。とはいえ出会いの翌日さっそく校内で勝久と遭遇しかけた莢子が“一か月後の再会”という演出をぶちこわさぬよう身を隠す場面で、彼女は確かに「やっぱり恋愛には舞台効果っちゅうもんが重要なんだからして」と明言しているし、腐れ縁らしき友人・佳葉が彼女の期待に水を差せば「あの時はたしかに恋愛のはじまりみたいな雰囲気があった!」と言って食い下がる。かなり輪郭の定かな、意外にもふつうの片想いなのである。
たとえば『動物のお医者さん』がそうであったように「忘却」シリーズにおいてもベタな色恋沙汰が描かれることはあまりない。勝久のワンテンポずれた物腰にはそもそも恋愛への関心自体を見出しにくいし、三本木というバディ(幼稚園以来の幼馴染で、人間関係はほぼ重複しているので勝久の覚えられない顔は基本的に彼が記憶している)とのズブズブな関係もその印象を念押ししているところがある。この二点は『動物』のハムテル(と二階堂)にも共通することだけれど、にもかかわらず――あるいはそれゆえに一層――私たちは彼らの描かれざる恋愛事情をめぐってついつい二次創作的な妄想をいだきがちであるようにも思われる。おそらくその理由の一つが、勝久もハムテルも作画上、美形と判断しうる余地を多分に残しているということだろう。こう何やら煮え切らない言い方になってしまうのは、佐々木作品においては女性も男性も基本的に美しく整った顔立ちで描かれるからにほかならない。もちろんこれはおおよそ少女漫画一般に認められる傾向で、仮にある人物の容姿が比較的冴えないとされる場合も、そのことはクセっ毛やそばかすなど副次的な特徴によって控えめに表象されるにとどまり、骨格や体形レベルで作品世界の標準的なボディデザインの型を逸脱することはおそらくあまりない。ただ、そのなかでも佐々木作品は容姿の差異を示す表徴がとりわけ徹底して希薄にされているのである。
たとえば同シリーズ中の一篇「山田の猫」に「日本的美観からいって美しいとはいえない」という設定の女性が登場するのだが、彼女が(変わり者であることは明らかであるにせよ)美人でないことを姿そのものから読み取るのは難しい。周囲の人物の反応から判断するか、もしくはその奇抜なファッションセンスが、特定の社会において設定された一般的な美の基準からの逸脱をかろうじて視覚的に表示しているにすぎない。つまり佐々木の作品世界において人物の美醜は物語設定上の単なる取り決めとして、登場人物の顔や身体からは完全に外部化され、非本質化されているわけだ。実際「君の名は」の莢子についても、勝久は「かわいい」、佳葉は「十人並み」、本人は「そんなにブスではないと思うんだけど」というように作品内の評価は必ずしも一定せず、読者がその容姿をどう見るかはある程度、個々人に開かれている。ましてや容姿をめぐる評価が作品内でほとんど明示されることのない勝久が「格好いい」かどうかを画に基づいて決定することはまず不可能であり、翻っては「モテている雰囲気はないけれど、実は格好いいのではないか」という仮説を個人的な妄想の範囲内で展開することも可能となる。密かに推す、という甘美なスタンスを読者に許すのである。ここで先述の「みんなは黒田くんのことをトンチンカンな人だと言うけれど/私はそれほどとも思わない」という言葉を思い出すならば、この隠微で両義的な言い回しは、公式設定の保証を欠いたまま「実は…ではないか」という曖昧な予感を萌していた読者の心理をそのままなぞっているようにも読める。この意味で、莢子は一種メタ的な視点で勝久を慕っていると言えるのではないか。要するに彼女の登場が勝久の作品内の立ち位置に大きな変革をもたらすことはないのであって、それは明らかに冴えない主人公に訪れた僥倖というわけでもなければ、かといって彼がモテることの証明材料にもならないのである(そういえば新海誠の『君の名は。』では主人公・瀧を、三葉の言葉で「東京のイケメン男子」としてはっきりと定義していたが、そうした含みのなさは本作と非常に対照的だと思う)。莢子の恋は作品の世界観をなんら揺るがすことなく、彼女のときめきは妄想する私たちのときめきと実にたやすく重なりあうことになる。
物語を読み進めよう。勝久との思いがけない遭遇を避けようとした莢子だが、間も悪く佳葉が声をかけてきたため彼の視界に入らざるをえなくなる。ところが莢子の顔を全く覚えていない勝久は当然のように彼女をスルー、さすがに衝撃を受ける莢子――「だってきのうのきょうで/仮にも私は命の恩人よ」。さらに追い打ちをかけるように、複数の知人から連続して名前を間違えられるという出来事も経て彼女は急速に自信を失いはじめる。「私は印象が薄いのかもしれない」「印象の薄い私と記憶力の悪い黒田くん/デートのたびに自己紹介してたりして」……それはそれで(メルヘンとして眺めるぶんには)素敵な気もするのだが、結局、莢子は約束の場所に行かないでおこうと決意してしまう。すでに夏休みに入っていて、二人が出会う機会はもうほかに残されていないにもかかわらず……。
一方、勝久は勝久で、ヒグマから逃げ出す際に莢子がルイの名を呼んでいたことを思い出すなどあって、彼女が以前から自分を知る高校の同級生であることをなんとなく察しつつあった。三本木たちにも心当たりを尋ねつつ、しかし確証の得られぬまま約束の場所に赴くものの、莢子は来ない。日も暮れていよいよ諦めかけたそのとき「ごめんなさい、おそくなって」との声とともに現れたのは、なんと佳葉だった――泥沼の予感である。
莢子は黒髪ショートカット、佳葉は腰まで伸びた巻き髪。さすがの勝久も第一印象で「ちがう」と感じる。しかしあのときは三つ編みにして頭にまいていたのだという佳葉の言いわけを受けて「ぼくのこの種の判断は8割がたはずれる/…ということはこの場合やはりこの人で「正しい」んだ」と、あっさり納得してしまうのだ。根深いコンプレックスに由来する自らへの疑いと諦めにより直観は否定され、判断は歪められる。まぎれもなく本作中もっとも切ない一幕だが、ここで目を引くのは「正しい」に付された鍵括弧である。文脈上、この“正しさ”は目の前の人物とあのとき自分を助けた少女との“合致”を基本的には意味していると思われる(この人で「合っている」という意味の「正しい」)。だが括弧による強調はこの語にもっと強い、ある種の倫理的なニュアンスを与えないだろうか――あたかも、あの日の少女に再会することが彼にとって一つの正義を含むかのように。
さて佳葉をカンシャク玉の少女と認めることにした勝久はその後、彼女を自宅の庭に誘い二人でルイに水浴びをさせて遊ぶのだが、その「デート」はいかにも不本意に課せられた義務として描かれていた。途中ジュースを買いに行くと言って抜け出した勝久は渋い表情でこう呟く――「デートというのは疲れるものだなあ」「いやしかし労働があるからこそ休みがありがたいのだ/楽あれば苦あり/人生とはそういうものだ」。佳葉との語らいは勝久にとって労働、義にかなうべき務めにすぎないのである。それゆえ家族からガールフレンドができたことを祝われても彼は浮かない表情だ。「なにか釈然としない/どこかまちがってるような気がする」。どこか間違っている――つまり間違いの所在は少なからず曖昧なのであり、したがってこの間違いは単なる“人違い”などではなく、もっと漠然とした状況全体の過ちを示唆していることになる。たとえばあの日助けてくれたのは彼女であると自分が認めただけで、特にそれ以上の手続きなしに「GF(ガールフレンド)」と呼ばれる相手を得るに至るという、この奇妙にオートマティックな進展そのものに潜む不正を。
しかし事態はもう少し複雑である。仮に状況そのものは不正であるとしても、あくまでも勝久自身は正しく義務を果たしていた。彼は自分を助けた者に対し正しい行いによって報いなければならないと考える。佳葉をガールフレンドとしてデートすることは、後述するように少なくとも佳葉という他者に対しては正しい応答の仕方なのである。問題は正しく応答すべき相手がほかにいるということ、つまりそれが間違った正しさであるということにほかならない。では本当の、正しい正しさとは何か――本作の面白さは、それが単にデートの相手を莢子へと修正することではないというところにある。
莢子は勝久の家の前を通りかかったとき、彼と佳葉のデートを目撃していた。そして勝久が「休憩」のためジュースを買いに出た隙に佳葉を呼び出し「黒田くんのこと好きでもないくせに!」と非難する(それに対する佳葉の「そんなことわからないでしょう?」という返答もすこぶる味わい深いのだが、ここでは深入りしないでおこう)。怒りに震え「私だって黒田くんに会うわ!!!」と叫ぶ莢子、そして後日ついに二人は揃って勝久の前に現れ、競い合うように自分が本物だと主張し「黒田くんどっち!?」と決断を迫るのだ。
莢子の登場によりさすがの勝久もどちらが本物かすぐに気づくのだが、なかなか答えを口にすることができない。なぜなら「一度佳葉さんを認めてしまった以上こちらに責任がないとはいえない/ましてどちらかを選ぶなんて」到底できないから。勝久の優しさと愚かさが典型的に示された一節だが、彼が逡巡しているうち莢子はふいに全てを諦めたような表情となり「私が嘘をついていたのよ」と言ってその場を去ってしまう。弁解のいとまもなく完全な悪者として残された佳葉、そして失意に沈んでゆく勝久……。
ところで、ふだんは一緒に遊びに出かけるほどの友人である莢子に佳葉がこのような常軌を逸した意地悪をしたのには幼稚園時代の因縁があった。近所に住むケースケくんという男の子に自分たちのうちどちらと結婚したいかと迫ったところ、彼は莢子を選んだのである。そのことを根にもっているのだろうと指摘され「フン! べつに私は器量が劣ってるから負けたなんて思ってないわ」と強がる佳葉に対し「わかってるわよ/みんな佳葉を美人だと思ってるわよ/それでいいじゃない!」と答える莢子。ここまでくると莢子の圧倒的な器の大きさが際立ってくるが、それはともかくここで興味深いのは、佳葉が自らの容姿に対してもつこの確固たる自信である。先ほども述べたように、佐々木の作品においては登場人物が「美人」であるかどうかを単純に作画から読み取ることは難しく、言語化された周囲の評価や、あるいは服装や振る舞いにかろうじて示されるにすぎない。そのなかで佳葉は繰り返し自分の容姿を誇り、また「みんな美人だと思っている」という他者の証言まで取り付ける。要するに美しさが取り決めでしかない世界のなかで彼女はその取り決めを力ずくで作り上げてしまったのだ。そうなるともはや私たちは佳葉を一義的に「美人」と規定せざるを得なくなる。もっとも勝久は、80年代風のトサカを豊かに湛えたその華やかな髪型を「前髪が(記憶のなかの少女よりも)うっとうしいような気がする」と一蹴しているし、三本木たちに少女の特徴を説明する際には満面の笑みで「かわいい」と言っていた割に、目の前の佳葉の美しさにはほとんど心を動かしていないようだ。とはいえ彼の陥った状況を客観的に形式化するならばそれは「誰もが認める美女との交際」なのであり、そしてそのことこそが「どこかまちがってる」と感じられていたのである。
美女=佳葉との交際の成就が侵犯したもの――それはまさしく私たちの妄想する自由にほかならない。具体的な恋愛事情を直接的には描かずそれをつねに潜在的なものに留めておきながら、格好よさの程度さえ読み手の想像に委ねるという作品の基本スタンスに対して、交際の成就はそこで与えられているはずの二次創作的妄想のポテンシャルを無効化してしまう。というより、ほとんど能動的に自らを「美人」としてはばからない佳葉の存在自体がそもそもそこに別種の法をもちこむ異分子なのだと言うべきかもしれない。佳葉が体現する異質な法とは「恋愛」のコードである。愛の告白等々の手続きを一切踏むことなく、また互いへの好意を宙づりにした状態で半ば自動的に恋愛関係を結ぶことは、それゆえコードの遵守という意味では「正しい」行いとなるだろう。だがそのコードは結局のところ異郷の法にすぎないのであり、したがって作品本来のコードに照らすならばその正しさはあくまでも間違った正しさでしかありえなかったのである。
それに対して作品本来のコードを体現する存在が莢子だ。その証拠は物語の最後、勝久と莢子の再会のシーンに見出されるだろう。夏休みも終わるころ、ふと思いついて莢子が約束の場所を訪れてみると、そこには勝久がいる。彼は彼女に謝るためにたびたびその場所を訪れていたのだ。「あの時きみが本物だとわかったけれど言えなかった」「私こそ約束をすっぽかしてごめんなさい…」とひとしきり謝罪が交わされたのち、莢子は勝久に思いを告げる――ところがそのとき勝久は「えっ」と驚き「そういう方向に話が進んでいたとは/こ…これは喜ぶべきことだよな/信じられないが」と戸惑うのである。佳葉を当たり前のようにガールフレンドとして受け入れていたことを思えば、彼のこのぎこちなさはいかにも奇妙に映る。だがこの困惑こそ莢子への正しさと佳葉への正しさとの根本的な違いを証し立てているのではないだろうか。先にも述べたように莢子は、実は格好いいかもしれない勝久をめぐる私たちの妄想とも重なりあう一種メタ的な視点から勝久に恋をしていた。しかしこのことは同時に、莢子と勝久が作品の内部においてアクチュアルに交際を成就させることを予め禁じるものでもあるはずだ。だからこそ勝久は莢子の告白を予期しえなかったのであり、また実際にも禁止は厳しく適用される――その時点ですでに、莢子は父親の転勤にともなって夏のうちに北海道を去ることになっていたのだから。
手紙書くねーと言って/浅羽莢子はハレバレと去っていった
莢子の去り際は実に爽やかなもので、あたかも告白を遂げた瞬間に恋心そのものがほどけてしまったかのようでもある。二次創作的妄想の自由を体現する者として、彼女は恋人未満のまま姿を消すよう運命づけられていたのだろう。最後のコマでは、かつて「GF(ガールフレンド)」ができたことを言祝いでいた際と同じ笑顔で「よかったねペンフレンドができて」と言いつつ、家族が勝久を取り囲んでいる(勝久は腕にルイを抱き、目には涙を浮かべている)。これは彼と莢子とが決して遠距離の恋愛関係にはないことの冷徹な念押しであるようにも読めるが、何度も言うようにほかならぬこの勝久の傷心こそが、莢子あるいは来るべきほかの誰かとの関係を私たちの側の妄想の領域に委ね、そこに自由を保証しているのだ。それが勝久の選んだ正しい正しさだったのである(ここで再び新海誠作品との対照を試みるとすれば、構造的にはむしろ『君の名は。』よりもはるかに共通点の多い『言の葉の庭』を想起するべきだろう。結末において主人公と教師はまさにここで言う「ペンフレンド」となるわけだが、そこでは恋愛の余地が曖昧に残されているぶんむしろ生々しい破局が「現実」として示唆されているようにも感じられた)。
実質はどこまでも仄かで、しかしあくまでも力強く「恋愛」を標榜しつつ、それでいて最後には風のように去ってしまう莢子の思いは確かに、作品世界の均衡と読者の妄想いずれにとってもあまりに都合よくチューニングされている。だが莢子の存在は(あるいは佳葉もそうかもしれないが)図式的に分析し解釈することの不可能な感性を構造の豊かな余白として携えている限り、決して抽象的な法ないしコードに還元されることはない。勝久に思いを告げるときの莢子の語りは「私はそれほどとも思わない」の奥ゆかしい屈託と響きあいながら、彼女と勝久の本質を美しく照らし出している――「私ね黒田くんの家の前を通ったことがあるのよ/ルイがものほしの柱のところにつながれていて/柱のまわりをぐるぐるまわって引き綱が短くなったところでころんで首輪にひっぱられていた/そこに黒田くんが出てきてアンパンでルイをひきもどそうとするんだけど/ルイはどうしても同じ方向にまわろうとするの/私それを見て黒田くんが好きになった」。
人を好きになるというのは、たぶん本当はこういうことなのだと思う。
参考文献
佐々木倫子「君の名は」、『家族の肖像』、白泉社(花とゆめCOMICS)、1985年。