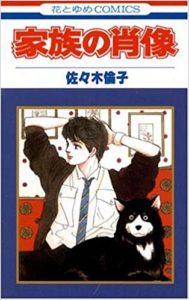不在の人、麻理——押見修造『ぼくは麻理のなか』における名前と身体 しだゆい
不在の人、麻理——押見修造『ぼくは麻理のなか』における名前と身体
しだゆい
2012年より『漫画アクション』誌上にて連載された漫画家・押見修造の『ぼくは麻理のなか』は2016年に全9巻で完結した。その年ちょうど新海誠監督の『君の名は。』が記録的なヒットを果たしたこともあり、完結に際しては「『ぼくは麻理のなか』は、現時点での入れ替わりの最新表現である」という新海のコメントを記載した帯が全巻に巻き直されている。とはいえこの作品をいわゆる「入れ替わりもの」と呼ぶことは、実のところ少々問題含みかもしれない。というのもそこに生じているのは必ずしも厳密な意味での人格の「交換」ではないからだ。名も知らぬまま密かに「コンビニの天使」と綽名していた女子高生・吉崎麻理の「なか」に入ってしまった「ぼく」=自堕落な大学生・小森功(の人格)が出会うのは——大方の予想に反して——小森功の姿をした麻理ではなく、麻理のことを知らないもう一人の小森功であり(第5話)、必然的に物語は「麻理さんは/どこに行ったんだ?」(第2話)という問いを軸に進められることになる。つまり、これは要するに不在の人をめぐる物語なのである。作品内で幾度となく反復される「麻理」という固有名のうちに私たちは「ゴドー」から「桐島」にまで至るそれらと同様の、ある予兆的な響きを聴き取らねばならない——すなわち麻理のなかにいる小森と、麻理がそこにいないことを唯一看破した柿口依、この二人の崇拝者によって待望される来たるべき者の名前として。
もっとも、その先に用意された結末は件の問いに対し、麻理は初めからここにいたのだと答えているように見える。そしてそれを踏まえたとき、この作品は一人の少女におけるアイデンティティの崩壊と再統合の物語として——つまるところ多くの押見作品と同様に思春期の終焉を描いたものとして、妥当にも読み解かれることになるだろう。するとこの場合「不在の人をめぐる物語」という当初の印象は、その不在ゆえに彼女が醸し出していた一種神格的なオーラとともにいわば単なるまやかしとして、エンディングを以て全くの無意味となってしまうのだろうか。このような、結末がそこに至るまでの過程をある意味で「裏切る」タイプの物語を解釈する際に、当の過程をすべて単純に切り捨ててしまってよいのだとすれば、しかしそれはあまりに貧しい見方と言うべきではないか。
そこで以下、私たちは『ぼくは麻理のなか』をあたかも初めて読む人のように、敢えて結末をいったん宙吊りにしつつ、あくまでも「不在の人をめぐる物語」として読み直してゆく。そしてここにはいない者であるとはいかなる事態であるのか、その存在=不在のありようを「名前」と「身体」という二つの観点から考えることで、それが本作の結末とその解釈においてきわめて重要な意味をもつことを示したい。
1.名前
自らが「コンビニの天使」と呼び崇拝してきた少女の身体で目覚めた小森功は、机の上に置かれた生徒手帳から彼女が「麻理」という名であることを初めて知り、その名を何度も口にしながら思わず涙を流す(第1話)。また学校にて、同級生の女子たちに挙動がおかしいことを指摘された小森=麻理の「わたしってふだん/どんな…だっけ?」という問いに、親友のももかは戸惑いつつ「麻理は麻理でしょ?」と答える(第4話)。
ほんの少し意識をチューニングするだけで、マンガ写植の慣習上ゴチック体で印字された「麻理」の二文字は謎めいた符牒のごとくページの端々に黒々と浮かび上がり、あたかも麻理という存在の一切の重みがその名一つに担われているかのようである。実際、その日の小森=麻理の言動に散々違和感を表明していたはずのももかが、いざふだんの麻理とは「どんな」なのかを問われても無意味なトートロジーではぐらかさざるをえなかったのは、反復されるその名前こそが彼女にとって麻理の本質であったことの証ではないか。このことは物語の終盤に至って前景化される母の問題を予め暗示してもいるわけだが、ひとまずそれは措いておこう。ここで重要なのは、麻理の名をただ繰り返しながら困惑するほかないももかたちに対し、決してその名を呼ぶことのなかった柿口依ただ一人のみが麻理の不在に気づきえたということだ。要するに麻理は麻理と呼ばれているその限りにおいてそこにいる、あるいはそこにしかいない、ということはつまり初めからどこにもいないのである。今ここにいないが必ずどこかにいるということ、それこそ到来を待望される存在たるための条件なのだとすれば、麻理は彼女を「吉崎さん」と呼ぶ依の「おまえ誰だ」という問いをもってようやく、真に不在の人となりえたのだった(第6話)。
この点に即して物語を追ったとき、依による呼称の微妙なブレが一つの仕掛けとして浮かび上がってくる。まず依は目の前の小森=麻理を端的に「小森」と呼んでおり、したがって彼女の発語する「吉崎さん」は、少なくともある時点までは原則として不在の人を指し示す三人称であった。ところが第14話、吉崎宅に泊まることになった依は小森=麻理の眠るベッドに潜り込み、初めて麻理に宛てて次のように語りかけるのである——「麻理/あのとき/いつもみたいに私が保健室のベッドの中に逃げ込もうとしたとき/あなたがいた」。そうして麻理は突然に依の手を引き、彼女を胸に抱きしめたのだという。
このとき小森=麻理は眠れないまま依の独白を密かに聞いていたのだが、第42話に至って明らかになるように、彼はそこで語られなかった(したがって本物の麻理でなければ知りようのない)出来事の細部までをなぜか知ってしまっていた。ここから、依は麻理が「どこかに行っちゃった」のではなく「その体の中に眠って」いるに過ぎないのだという仮説を提示する。たしかにこの見立ては、結末に照らす限り真相をおおむね正しく見抜いていたことになるだろう。だが少なくともこの時点では、依の認識はむしろ後退していると言わねばならない。というのも以後しばらくの間、彼女はそれまで抑え込んでいた欲求を一気に開放したかのように学校でも小森=麻理に屈託なく「麻理」と呼びかけ、いかにも友達然として振る舞うようになるのだが、それによって彼女は小森功という人格をいないことにするだけでなく、麻理をその名で呼ぶことによってそこにいることにするという、まさしくももかたちと同様の過ちを犯してしまってもいるからだ。
この事態について考えるために、第42話における事のなりゆきを「呼称のブレ」に着目して少しばかり丁寧に追ってみよう。
保健室のことに話が及ぶ直前、依は不意に「麻理さん」という言葉を口にしている。これは専ら小森の用いる呼称であり、ここで依は彼の言い方をいわば引用したのだと考えられる。第三者について、会話相手による呼称を敢えて用いつつ言及するというのはたしかによくあることだろう。しかし第14話以降も三人称的な言及では一貫して「吉崎さん」という呼称を使用していたことに鑑みれば、この何気ない引用は彼女の意識に萌しつつあった何らかの変化を示していると見るべきではないか。事実、続けて依は目の前の小森=麻理に、あたかもそれが麻理その人であるかのように語りかけている——「あのとき麻理が…保健室で抱きしめてくれて/初めて私に近づいてくれて/ほんとにうれしかった/なのに私…/遠くから見てただけで/ごめんね」。保健室の一件について小森=麻理が知るはずのない細部にふれ、それを根拠に依が「麻理さんは中にいる」のだと言い出すのはその直後のことだが、おそらくこの時点ですでに依は、そこにいるのが他ならぬ麻理なのだと暗黙のうちに考えはじめていたのだ。言い換えれば、依が目の前の小森=麻理を公然と「麻理」と呼びはじめたことは実のところなんらラディカルな変節ではなく、一種の惰性から密かに進行していた認識のゆるみがそこでたまたま顕在化したに過ぎないのである。
したがって真の転機はむしろそのさらに後から訪れる。いくらかの波乱ののち、依はそこにいる者を再び「小森」と呼び、かつそこにいない者を名指す三人称的な呼称として「麻理」という名を用いうるようになるのだ。もはやこの固有名は(少なくとも依によって発語される限り)麻理をそこに呼び出すための呪文ではなく、ゆえに麻理はここに至って初めて麻理として不在であることが可能になる。このことは逆説的にも、彼女の存在をその固有名の軛——すなわち「麻理(の存在)は麻理(という名)」であるとする呪いのようなトートロジー——から解き放つことを意味するだろう。麻理が麻理として不在であるとは、すなわち彼女が自らの名前の外、その名が呼ばれる今この場所ではないどこかに存在を認められるということに他ならない。
2.身体
麻理を不在の人として認めること——しかしながらそれは、裏を返せば今ここに現前している彼女の身体が麻理であるとは決して認めないということでもある。そこにあるのはたしかに麻理の(所有する)身体かもしれないが、それ自体は麻理ではない。そもそも麻理がそのなかにいる/いないという表現自体、一つの人格が特定の身体から切り離されてそれなしに存在しうることを明らかに前提したものだ。その意味で依の見方はきわめて心身二元論的、かつ個人の同一性を「心」のほうにのみ認めるいささか偏狭なものとも思われるかもしれない。むしろ最後まで麻理が麻理であることを疑わないまま戸惑い、そして排除したももかたちのほうが(外見や名前以上の麻理の「内面」にかんして何ら具体的な認識をもっていなかったことを含めて)よほどラディカルだと言って言えないこともないだろう……とはいえ、実のところ問題はそれほど単純ではない。
まず確認しておくべきは、麻理の身体のなかに小森功という人格が入り込んだのだというのはあくまでも小森=麻理の説明に過ぎず、依は必ずしも最初からそれを信じ込んだわけではないということだ。第8話、自分が小森功であることの「証拠」を見せろと言われた小森=麻理は依をかつて自分が住んでいたアパートへと連れていき、忍び込んだ留守中の室内で学生証を見せながら彼の所属や出身地を諳んじるのだが、それに対し依は次のように返答する――「…べつに/小森功とかいうヤツの個人情報いくら並べられてもね……/その身体が本物の吉崎さんだって証拠にはなってないし」。つまり少なくともこの時点では、依は目の前の存在が身体ごと偽物である可能性も考えている。そして「この身体は絶対麻理さんの身体だよ」と(さしたる根拠もなく)なおも主張する小森=麻理に対し「……信じない」と冷たく言い放つのである。
ところがこの疑念はすぐさま放棄される。今もこの部屋に住むもう一人の小森が戻ってきたため依たちは急いでベランダへと逃げ込むのだが、そこで二人は彼が帰宅早々にマスターベーションを始めたことに気づく。そして小森=麻理がその姿をおそるおそる覗こうとしたとき、依はその目をさっと塞いで「吉崎さんの眼球で…見るな!」と叫ぶのだ。
いかにして依がそれをたしかに「吉崎さんの眼球」であると認めるに至ったのか、その経緯は一見したところはっきりとは描かれていない。しかしそれに先立つあるシークエンスを一つの手がかりと見ることはできそうだ。それはベランダで息を殺す二人の汗ばんだ腕が密着し「ぴと‥」と音を立て、続いて目を伏せたままの依が「…さいあく…」と呟く二つのコマである。この呟きは漠然と現在の状況全体に向けられたものである可能性も当然あるのだが、直前のコマで二人の身体的な接触が擬音とともに強調されていたことの意味を強いて深読みするならば、次のようにも解釈できるだろう——すなわち依は自らに触れる身体が麻理のものに他ならないこと、信じまいとしていたその事実をまさしく身体でもって感じ取ってしまった、それこそが「さいあく」だったのではないかと。
もっとも、仮にその身体が偽物だったとしても麻理がそこにいないということに変わりはないばかりか、少なくとも身体だけはここにある今の状況に比べて、それがまるごと偽物であった場合のほうがむしろ事態はより「さいあく」のようにも思われる。ところが依はそう考えない。なぜなら彼女の絶望はあくまでも、それがたしかに麻理の身体であるにもかかわらずそこに麻理(の人格)がいないということ、そのズレにこそ起因しているからだ。つまり依にとってその身体が「本物の吉崎さん」であるとは、単なる物理的な同一性以上に自分がかつてその同じ身体に抱きしめられたということをまずもって意味するのであり、しかし他方では、その身体が今やあの抱擁の記憶を共有していないというただその一点のみをもって、それが麻理であるとはもはや認めることができないのである。
したがって依は決して麻理の人格をその身体から単純に切り離して考えているのではなく、むしろ自分を抱きしめた他ならぬこの身体とその記憶との結びつきそれ自体にこそ麻理が麻理であることの条件を見出していると言うべきなのだ。おそらくここに、ももかと依の最大の差異があるのだろう。そもそも依が小森=麻理を「おまえ誰だ」と問い詰めたのは、それまで一度も使われたことのない「カワイイ」という語が口にされたことに加えて、泣きながらももかに抱き着くという、依曰く「絶対あり得ない」行動も原因となっていた。そして依のこのような断言がそれでも自分はたしかに抱きしめられたのだという自負に裏打ちされていることは明らかである。実際ももかは小森=麻理が彼女の背中に手を回した瞬間に「イヤッ」と言って身体を押しのけているし、もちろんこれはそのときの「触り方がキモ」かったからだと言われるのだが、それを措いたとしても、彼女は麻理の身体についてもともと何も知るところがなかったのではないか。たとえ「友達」としてのカジュアルな接触は日常的にあったにせよ、彼女の身体がもつ剥き出しの物質性に生々しく不意打ちされること——その経験こそまさに依の特権性にほかならないのだが——など、おそらく一度もなかったのだ。私たちは受肉した存在であると言いながら、本当は不気味でたまらないはずの他者の身体の異質さをふだんはできるかぎり覆い隠すことで日々を送っている。そんなにも薄くて軽く、また透明な身体は、それゆえ名前とほとんど見分けがつかない。こうして麻理の存在は、絶えず反復されるその名前のなかにいともたやすく閉じ込められてしまう。身体の消去と固有名の呪縛はまさしく表裏一体なのである。
*
ここにはいない者であるという麻理の存在=不在のありようは、したがって一方ではその存在を「麻理」という名前の軛から解き放ちつつ、他方ではその不在をたしかにここにある身体の現前と対比的に結び付けるという二重のプロセスを通じて成立している。私たちのアイデンティティを担う最も根本的な支持体にほかならない「名前」と「身体」というこの二つのファクターは、やがて物語の核心をなす主題として前面に浮かび上がり、結末における解決——麻理は初めからそこにいたのだということ——もまた、まさにその延長線上に導き出されることとなる。ゆえに麻理の不在とは決して、単なるフェイクの印象として最終的に否定されてしまうだけのものではない。それどころか彼女の人格が同一性を取り戻しつついっそう高次の統合へと至るためには、正しく不在でありうるという可能性の獲得がどうしても必要だったのである。結末に明かされる真相が少なからず「サイコな」ものであるとしても、そこに至る道のりは必ずしも「精神的な」ものではない。むしろ常に精神の残余としてある名前と身体をめぐってこれほどにも精密なドラマを紡ぎあげたという、その点にこそ本作の最大の達成は見出されるべきだろう。
参考文献
押見修造『ぼくは麻理のなか』全9巻、双葉社(アクションコミックス)、2012-16年