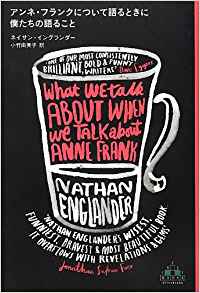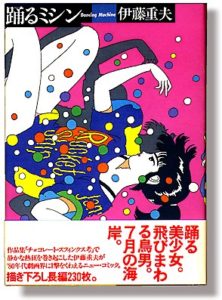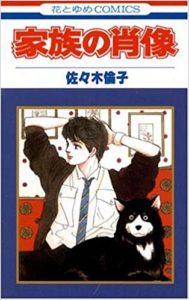象がそこに佇んでいる――別役実の動物論 しだゆい
象がそこに佇んでいる――別役実の動物論
しだゆい
別役実の『象』(一九六二年初演)は病院を主な舞台に、一人の入院患者(「病人」)とその甥である「男」の対話を軸として展開される戯曲である。病人はかつてヒロシマで被爆し、時を経て病に倒れるまではときおり大道に立って背中に負ったケロイドを見世物にしていた。男もまた同じく「ヒバクシャ」であるが、叔父とは対照的に自らはただ息を殺してひっそりと生きてゆくことを望み、また叔父にもそうあってほしいと思っている。一方はおのれの実存を意味づけるために過剰な自己露出へと赴き、他方は自分の実在感を極限まで無化することで生の無意味をじっとやり過ごそうとする。互いにベクトルを異にしつつも同じ被爆という経験によってもたらされた歪みのかたちを薄暗い抒情とともに描き出したこの傑作には、ところでどこにも象が登場しない。「象」という言葉すら、表題を除いては一切現れない。もっとも、それ自体はさして珍しいことでもない。タイトルが内容とほとんど、あるいは全く無関係に見える作品などいくらでもある。となると重要なのはなぜ『象』なのかということ――つまりこの作品に固有の命名理由を問うことであるが、それもさしあたり措いておきたい。私たちがまずもって立ち止まらねばならないのは、そのように問う者を襲う、奇妙な疚しさである。
なぜ『象』なのか。この問いがどこか白々しく響くのはおそらくそれが答えの探し方を予め定めてしまっているように見えるからだ。はじめに『象』というタイトルを認め、しかしそのもとに提示されるテクストのどこにも象そのものを見出せなかったとき、タイトルの意味を問う者はそこに何らかの象的なものを探し当てようとせずにはいられない。要するに「象」を一種の隠喩として解釈しようと試みるのである。実際、それは決して難しいことではないだろう。すなわち『象』というタイトルにおいて別役は自らを見世物としてきた病人の、老いとともに身体も衰えケロイドもシミだらけになってしまった鈍重な実存のありさまを動物園に寂寞として佇む老象の姿に重ねあわせているのであり……等々。
とりたてて問題のある解釈とも思われない。ところが、この考えは一方である言い知れない抵抗感を呼び起こす。それはその種の解釈が単に安易すぎるからとか、被爆した人間を動物に喩えることに素朴な倫理的疑問を感じるからという以上に、隠喩(もしくは何かを隠喩として解釈すること)一般にときとして伴いうるある種の下品さ、猥雑さがここで不意に立ち現れてくるように感じるためである。この「感じ」はたとえば何か棒状のモノによって男性器を暗示する類いのごく下らない冗談を想起するとわかりやすい。たしかにそれは最も低級な隠喩ではあるが、低級であるがゆえにおよそあらゆる隠喩が潜在的に含意する独特の運動をすぐれて戯画的に示しているようにも見えるのだ。それは隠すべきものを隠すことによって暴くという、一種の欺瞞的な操作である。
あるものを別のものによって表わすことで、隠喩は前者のもつ意味や本質をいっそう露わに見せることができる。しかしこうした操作は、裏返せば当の対象をそれ自体としては見えなくすること――さらに言えば「直視すべきではないもの」へと、いわばいったん貶めることで成り立っているのではないか。何かを隠喩として利用することへの批判はこれまでもしばしば行われてきたが(たとえば「病い」をめぐって)、おそらく隠喩を用いて指し示される側の対象もまた、その可視化されつつ不可視化される運動において、ある意味で辱められている。つまりそれが動物の隠喩であろうとなかろうと、喩えるという操作を通じて彼の存在に恥の烙印を押していることにこそ、この解釈の不埒さがあるのだ。そして実際、この作品においてはケロイドがまさしく「隠すべきもの」となったとき、病人の人生は明確に破綻をきたしはじめるのである。具体的には「原水爆禁止大会」の演壇上で彼が傷痕を披露してみせたときから――「なぜあの時みんな拍手をしなかったんだい?/熱烈な拍手をするだろうと……ね、思ってたんだよ。/観客はシュンとしている……。/〔中略〕気が付いたら観客は、だあれも居ないんだよ。/だあれも……居なかった」「あの原水爆禁止大会があってからいけなかった」「俺はそれから、見物人を喜ばせようなんて考えなくなった」。
あるものを隠すことでいっそう露わにするというこの欺瞞は、したがってある種の偽善をも含んでいる。ケロイドを見て喜ぶのは政治的に正しいことではないという意識の高まりが、逆説的にも病人から生きることの支柱を奪ってしまうというわけだ。原水爆禁止大会のとき以来、彼は観客がケロイドではなく自分の「眼」を見ていることに気づく。人々はケロイドを直視することをせず、ただ眼を媒介として、彼の自己意識を通じて間接的にそれを捉えようとするのだが、それはそうすることでその傷のもつべき意味をよりよく見ることができるからにほかならない。
ところがそのことをすでにはっきりと感じ取っていた男は、叔父に対し苛立ちを露わにしつつ次のように言い放つ――「もう誰も僕達を殺してくれる人なんか居ないんです」「「ケロイドが、伝染るといけないから」なんて言う人が居ますか?/誰もそんなこと言いやしない。誰も言いやしませんよ。/〔中略〕ねえ、それじゃまるで僕達は愛し合ってるみたいじゃありませんか?/そうでしょう。僕達を殺したり、僕達の悪口を言ったりするのは禁じられているんです。そういうシクミになっているんですよ。だからみんなニコニコしています。愛し合っているみたいなんです」。ところが病人にはこの理屈がわからない。彼は甥の言葉を受けて、嬉しそうに答える。「そうなんだよお前、俺達を愛してくれる人も居るんだよ」「俺達は愛し合っているんだよ」……そして最後の最後まで、その証しを自らの身体によって手に入れようともがくことを止めない。二人のコミュニケーションはこうして、どこまでもすれ違い続ける。
自らをできる限り不可視化することによって、直視しうる理解可能な存在として包摂されることを選んだ男は、「隠すべきものを隠すことによって暴く」という隠喩的なまなざしのシステム(「シクミ」)を受け入れ、そこに取り込まれたいと願う。それに対し自らの身体をそのものとして視線のもとに晒そうとする病人は、結局のところ当の視線によって不可視の領域へと追放されざるをえない。したがってそれを「象」という隠喩によって再び理解可能なもののうちに取り込もうとすること――彼の生のありようをいくつかの属性に還元しそれを象として表象し直すことは、この悲劇に対する端的な裏切りと言うべきだろう。私たちは彼を彼として直視すべきなのであり、裏返して言えば同時に「象」なるものについてもまたそれを象そのものとして直視しなければならない。作品の入り口に佇む象の姿を、その一見した無意味の様相のまま佇むに任せておく必要があるのだ。ゆえに私たちが問うべきは「なぜ象なのか」よりもまず、別役にとって「象とは何か」ということである。そしてそうすることで象がそこに佇んでいることの意味が再び、隠喩という予定調和的な解決とは別様の仕方で見出されることになる。
*
評論集『電信柱のある宇宙』に所収の「私と動物」と題する短いエッセイを、別役はある一本の電話に関するエピソードから書き起こしている。電話の主はさわやかな若い女性の声で「アンケートにお答えください」と言い、続いて有無も言わさず「猫はお好きですか」と問う。それに対し別役が「嫌いです」と答えると、次は「じゃあ、犬はお好きですか」と訊かれる。やはり「嫌いです」と彼が答えたところ、女性はなぜかひどく戸惑った様子で「何故ですか」と言うのだ。それでしばらく黙って考えてみたのだが、向こうが沈黙に耐えかねたのかそのまま、電話は切れてしまったという。
これが実際にあった話かどうかは措くとしても(なにしろこれは別役実のエッセイなのだから)、続けて綴られる動物観そのものはあくまで彼自身の切実な体感を伴っているように思われる。「どんな動物が好きですか」と訊かれて「好きな動物はいません」としか答えることができないのは、何らかの動物を飼ったり、触ったり、抱いたり、可愛がったりする気が彼にはないという意味であり、それは必ずしも「関心がない」ということを意味しない。関心の有無について言うなら、彼はむしろ動物に対して「かなりの興味を抱いている」というのである。「たとえば」と彼は言う「牛や馬や象など、私よりも図体の大きい動物に出合うと、そのことだけで手もなく感動してしまう」。しかしその感動を「好き」などという言葉に置き換えることはできない。好きかどうかと問われれば「私は、象はやはり「嫌い」の方に分類するだろう。しかし、出合って感動はするのである」。
別役によれば「象を象たらしめている要素」は「大きい」ことと「汚い」ことの二つに集約される。「つまり、私が象から受ける感動というのは、そうした救い難い汚さを、かくも大きくまとめあげた、と言う点にあると言ってもいい」「生きていること自体が面倒臭そうであり、もっと言えば、それらが象としての形になっていること自体が、面倒臭そうである。もしかしたら象は、毎日、自分が象であることに、背筋の寒くなるような思いをしながらいきているのではないか、とすら思われる。こうした象の、象たるがゆえのやりきれなさが、私にはよくわかるのだ」……。とはいえ、隠喩的な解釈を拒む私たちにとって重要なのは、別役が象の本質をどう捉えているかということではない。むしろ注目すべきはこの「わかる」という表現である。彼は「好き」という言葉に還元することのできない動物への「興味」や「関心」を「理解」と言い換えていた。すなわち「どんな動物が好きですか、と聞かれても、好きな動物はいません、と答える以外にないが、どんな動物を理解していますか、と聞かれたら、さほどはにかむことなく、象です、と答えることが出来ただろうと思う」と。
したがって、ここで問題にされているのは愛を伴うことのない理解、むしろ愛と相反するような理解のありかたである。別役は動物を「好き嫌い」で判断する人を「余り信用したくない」と述べ、猫や犬が「好きです」とか「家族同様にしてます」と言って愛撫している姿を見ると「ぞっとする」とさえ言い放つ――「それは確かに「好き」には違いないだろうが〔中略〕「理解はしていない」に違いないからである」。
ただしこの別役のスタンスは、動物に対する一方的な愛玩は人間のエゴである等々というありふれた道徳的非難とはおそらく似て非なるものだ。動物のことをよりよくわかっているからこそ自分は敢えて突き放した態度をとるのだという訳知り顔のマウンティングなら、どこにでも転がっているだろう。それに対し別役が動物に対する関係を「理解」という言葉で表明するとき、そこには絶望的なまでのディスコミュニケーションの感覚が避けがたく伴っている。重要なのはそこである。エッセイの末尾で別役は、はじめて自分の娘と上野動物園に行ったときのことを次のように語っていた。彼は「娘を抱き上げて、象を指さして言った。/「ほら、あれが象さんだよ……」/しかし、それ以上、何をどう伝えていいのか私にはわからなかった。動物は、難しいのだ」。
動物は難しい――たとえそれを「理解」できたとしても、その理解は言葉によって伝達しえないものであり、したがって意味へと終着することがない。ゆえに象が象として理解されるというとき、それは先に見た「隠すべきものを隠すことによって暴く」隠喩的なシステムへの包摂とは無関係なところで生じている。まるで愛し合っているかのような、そんな見かけを伴うこともない、それは社会の「シクミ」によってもたらされる理解可能性とは全くかけ離れた、ほとんど無理解と見分けのつかない「理解」なのである。こうして私たちは『象』というタイトルの意味をめぐる最初の問いに帰り着く。すなわちそれはあの病人を(あるいはそのほかの誰かを)象として見ることを禁じながら、しかし象を見るように見ることを厳格に指定しているのではないか。別役にとって象とは、いわばある種のまなざしのモデルなのだ。愛することも包摂することもなく、いかなる証しも欠いた状態の、しかし「理解している」としか言いようのない他者への関係。たとえば男は叔父である病人の「ケロイドの裸男」としての生き方を嫌悪しつつ、たしかにそれを「理解」していた――あるいはどうしようもなくわかってしまったのだと思う。そのような極限的で、ともすれば絶望的な「理解」の関係が作品のうちで(男と病人、病人と妻、妻と通行人等々もしくは彼らと私たちのあいだに)張りめぐらされる、というかたちでそこには象が偏在している。彼らは、そして私たちはそうした関係性において、隠喩ではなく――ということはいささかも象に似ることなしに、象になるのだ。テクストの門口に印字された一頭の象の存在はおそらくそのための導きとして、暗い予感のようなものを帯びたままじっとそこに佇んでいるのである。
註記
本稿における引用はもっぱら以下の二冊からおこなった。なお原文における傍点箇所は太字に置き換えている。
別役実『別役実I 壊れた風景/象』ハヤカワ演劇文庫、2007年
別役実『電信柱のある宇宙』白水uブックス、1997年
ところで本稿は副題に「別役実の動物論」と銘打ちながら事実上『象』の読解に終始したものであり、看板に偽りありとまでは言わずともいささか不十分の感は否めない。別役の動物に関する考え方を真正面から論じるためには『獏』などをはじめ動物がより直接的なモチーフとして登場する他の戯曲に加え、諧謔に満ちた動物(偽)誌『けものづくし 真説・動物学大系』(平凡社、1982年)のとりわけ「動物園」の項を取り上げないわけにはいかないだろう。ここで別役は「私と動物」の末尾に触れられた「我が子に象を見せる」という経験をより詳細に、発展させたかたちで論じている。
また上記の引用文献とは別に、本稿の準備段階においてジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリによる『千のプラトー 資本主義と分裂症』(宇野邦一ほか訳、河出文庫、2010年)第10章を再読していた記憶が、とりわけ結論部の「象になる」なとどいう(唐突かつ少しばかり軽率な)記述に影響していることもここで白状しておく。とはいえドゥルーズもまた別役と同様、愛玩動物に対し強い抵抗感を表明してはばからなかったことを思い出すなら、これはあながち無根拠な参照でもないかもしれない。この点は別稿を期したい。